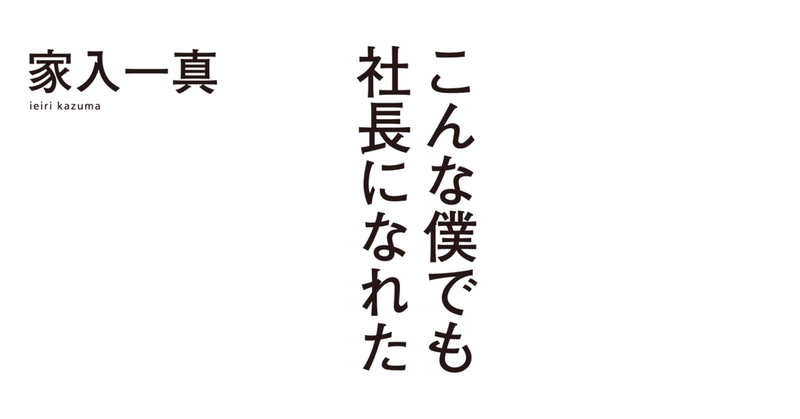
こんな僕でも社長になれた - 第二章 「ひきこもり」だったあの頃
チン騒動で転落
それは僕が小学校一年生のときの出来事だった。
当時僕たちは、もっぱら家の近所にあった寂(さび)れた神社で遊んでいて、その日も例によってランドセルを置くなり、鉄砲玉のように家を飛び出した。ところがあんまり急ぎすぎたのか、僕が到着したときには、まだ一人も友達の姿はなかった。
(みんな、まだ来とらんちゃが……)
空は曇りで、妙に蒸し暑い初夏の日だった。ただ待つのも面白くないので、何となく神社の境内をうろうろ歩きまわっていたちょうどそのとき、神社の裏手の雑木林で、僕は思わぬ光景を目にした。
中学か高校の制服を着たカップルが、何となく寄りそった感じで、地面に怪しげに座り込んでいたのだ。二人は、イキナリ現れた僕を見てあからさまに動揺していた。そんな二人の様子に、何も分からない僕もつられて、どぎまぎした。すると突然、男子のほうが、聞いてもないのに、僕に妙な弁解を始めたのだ。
「……べ、別になんもしとらんばい。この子が怪我したけん、手当てしてやりよっただけっちゃ」
そんなこといきなり言われても僕には何のことだかサッパリだった。だけど、その男子生徒のあまりの動揺ぶりに、とにかく僕は、何だか分からないけど、見てはいけないものを見てしまったらしい、という罰の悪さを感じていた。そんな僕の様子を知ってか知らずか、男子生徒はさらに言った。
「千円やるけん、見たことは誰にも言わんどって」
当時の一ヶ月の小遣いが百円だった僕にとって、その十ヶ月分の額にも相当する千円は、言うまでもなく大金だった。でも、そうは言っても、予期せず提示された、金銭の絡んだ生々しい取引に、すっかり度肝を抜かれてしまっていたそのときの僕はというと、千円も受け取らないまま、とにかくその場から一目散に走って逃げ出したのだった。
走って、走って、雑木林を抜けて、神社を出て、走って、走って……鳥居から延びる一本道で、ちょうどやって来た友達と、ばったり出くわした、その瞬間に、僕は雑木林で目にしたこと、耳にしたことを、洗いざらいぶちまけたのだ。
「今、そこに変な男子と女子がおったっちゃ! 千円やるけん、見たことは誰にも言うなち言われたんばい!」
「家入君、何を見たん?」
「ぼ、僕は何にも見とらんばい」
「えー、何か見たんやろ。何も見とらんのに千円やるち言うわけないやろ。家入君エロかー」
「本当に見とらんっちゃが」
仲間を得て一気に強気になった僕は、その後すぐにその雑木林に駆け戻ったけれど、もうそこに、あの男女の姿はなかった。
今となって思えば、あれは僕の度が過ぎたおしゃべりを見かねた神様が、僕に与えた最初で最後の試練だったんじゃないかと、そんな風に思えてならない。誰にも言うなと言われたことを、言われた通り内緒にできるか、それとも、話してしまうのか。
差し出された千円こそ受け取らなかったけど、結局やっぱり、後者を選んでしまった僕。
それから何年もたった後、試練をクリアできなかった僕に、神様は一つの罰を与えた。
口は災いの元──そんな言葉を嫌が応にも思い知らされる、それはそれは痛烈な罰だったのだ。
「おまえ、チン毛生えとっちゃが」
中学二年生の、夏のある日。当時仲の良かった友達に、僕が何気なく口にした一言だった。
念のために説明しておくとこれは北九州弁で、「おまえ、チン毛が生えているんだろう」という意味だ。
もちろん可愛い冗談のつもりだった。いつもと何も変わらない悪ふざけのつもりだった。ところが、この一言に僕の友人はぶち切れたのだ。顔を真っ赤にして、
「なんかちゃぁ(なんだと、の意)!」
と激しく喰って掛かってきたのだ。……空気を読めない愚かな僕はというと、そんな取り乱す友達の様子を、なお一層面白がって、
「チン毛チン毛~チン毛~チン毛~」
と再び執拗にからかったのだった。両手を、肩甲骨の辺りでひらひらさせながら。
怒り狂った友達は、ついには僕に強く体当たりしながら、汚い言葉を浴びせてきた。そのときになって僕はようやく、冗談じゃ済まされそうにない、ということに気が付いたのだった。
改めて言うのも何だけど、当時の僕は栄養失調じゃないかと疑われるくらいからだが細く、身体を鍛えるために無理やり入部させられた剣道部も、どうしても人を叩けなくて一週間で退部した根っからの臆病者。だからこのときも、調子に乗って相手をからかうまでは良かったものの、その後の友人の思わぬ激昂(げき こう)ぶりに、ただただ恐々として、言われるがままに詰め寄られていた。どうにかこの場を切り抜けなくちゃと、取り繕うように愛想笑いを浮かべてみるものの、
「おまえ、俺んこと馬鹿にしとんかちゃ」
……皮肉な結果に。そんなわけで、事態は最悪の展開を迎えたのだった。
翌日から僕とそいつは絶交。チン毛の有無で、絶交してしまったのだ。
それだって最初のうちは、二、三日もすればきっと元通りになる、そんな風に安易に考えていた。ところが三日、四日と待ってみても、状況は一向に変わらない。朝、教室で顔を合わせた途端に、鋭い目つきで僕をきっと睨み付け、敵意をむき出しにしてくる友達。
(やばい……このままじゃ凄くやばい)
僕は何度も、正直に謝ろう、許してもらおうと考えた。でも、生まれて初めて味わった、友人からの厳しい拒絶に、すっかり縮み上がってしまっていた僕はというと、あの一件以来、そいつにたったの一言さえ、声をかけることができなくなってしまっていたのだ。
そうこうするうちに、事態はさらに悪い方向に転がった。どう声を掛けようかもたもた悩んでいる間に、当時、僕と一緒につるんでいた他の友人たちまで全員、一斉にそいつの味方についてしまったのだ。実際、仕掛けたのは僕のほうだから当然といえば当然なんだけど、昨日までは友達だったやつらが突然、「元」友人という冷たい目で、僕を見るようになってしまった。結局、僕の周りには、ただの一人も友達がいなくなってしまったのだ。
それからというもの、僕の世界は一変した。
学校へ行っても、「おはよう」と声を掛ける相手がいない。休み時間にプロレスの技を掛け合う相手がいない。昼休みにドッジボールをする仲間がいない。いたずらの策を練る相手がいない。一緒に下校する仲間がいない。ゲームを貸し借りする相手がいない。「家入君」そう、名前を呼んでくれる相手がいない。
友人たちと僕を繋いでいたたくさんの見えない線が、いきなり全部、ぷちっと、切れてしまったのだ。
昼休みになると、ボールを小脇に抱えて競うように教室を飛び出していく「元」友人たち。ついこの前まで、その中には当たり前のように僕がいて、一緒になってボールを投げ合っているはずだった。でも、僕はもうそこにはいない。
(なんでこんなことになってしまったんだろう……)
グラウンドに出る代わりに、人の少ない図書室へ逃げ込む僕。寂しくて、惨めで、下を向けばどんどん涙が溢れてくるから、本を開いていても、字なんて追うどころじゃないのだった。
鏡の前で笑顔の練習
それまでの僕は、ちょっとくらい勉強や運動が苦手でも、学校を嫌だと感じることは一度だってなかった。でも友人たちから完全に孤立してしまってからというもの、学校は苦痛以外の何物でもなくなった。できることなら行きたくない、休みたいと思うのに、羞恥心とか、意地とか、プライドとか、色んな感情が絡み合って、しばらくの間僕は、自分の身に降りかかっている事態を、正直に家族に打ち明けられなかった。落ち込んでいることを悟られないように、家では何食わぬ顔をして、お調子者で、ひょうきんな僕を演じ続けていたのだ。
だけども、親とは、家族とは、本当に偉大なのであって、後から聞いた話では、僕の両親、妹、弟は、もう随分早いときから、僕の異変に気づいていたらしかった。なのに一方で当の僕はというと、気付かれていることに気付く余裕さえ、まるでなかったのだ。
もちろん、僕は僕なりに、何とかそんな状況から抜け出そうと、必死でもがいていた。完全に居場所を失ってしまった教室の中で、仲間にもう一度、僕のことを受け入れてもらえる方法を探した。で、ふと、ひらめいた。
(……前と同じようにやればいいんだ)
前みたいに、自然に友達の肩を叩いて、自然に声を掛けて、自然に輪の中に入る。うまくやればきっと、かつての仲間たちも、僕を何気なく迎え入れてくれる、そう考えたのだ。
ところが、いざ実行に移そうというときになって、僕は途端に途方にくれた。
(……あれ、どうやるんだっけ?)
前までの僕が、どんな風に友達に声をかけていたのか、どんな風に呼び止めて、どんな風に話をしていたのだろうか、どんな風に笑っていたのか、さっぱり思い出せないのだ。
相手とどの程度近づいていたか、何の話題を持ち出していたか、相手のことを何と呼んでいたか、僕はどんな風にしておどけていたのか、以前まで何気なく自然にやれていた動作を、僕は何一つ自然に、できなくなってしまっていたのだ。
嘘みたいな話だけどその日から僕は、家にいる間、家族に隠れて鏡の前で何度も繰り返し「笑顔」の練習を始めたのだった。最初に目を閉じて思い出す。ちょっと前の自分。たくさんの友達に囲まれて、心から素直に笑えていた僕を。口は、目は、どんな形だったか。頬はどんな風に上げて、眉をどんな風に下げていたか。そしたら目を開けて、同じようにやってみる。口元、目元、頬を上げ、眉を下げる。
ところが、同じようにやっているはずなのに、どうしてもぎこちないのだ。笑っているはずなのに、情けない、泣き顔みたいになってしまうのだ。
今となって考えてみれば当然のことで、自然な仕草なんて意識すればするほど不自然になる、そんなの当たり前だ。でも当時の僕はというと、とにかく何とかしなくちゃという強い思いがひたすら空回りを繰り返し、挙句の果てにはどんどん深みにはまっていく、そんな、ひどい悪循環の真っ只中にいたのだった。
そんなこんなで僕の中学生活後半は、ほぼ泣き顔と、泣き顔みたいな笑い顔の思い出ばかりを残して終了。あの手この手で再起を試みたものの、結局全部、駄目だった。
……それもそのはず。僕の中学生活は、その後に続く長い長いトンネルの、ほんの入り口に過ぎなかったのだ。
一人ぼっちの高校生活
例の一件以来、中学での僕はというと、必然的に勉強に励む以外、やることがなくなってしまったのだった。その結果、中学三年生の僕は普通受験を経て、近所でも難しいとされる県立高校に、見事合格。
中学卒業、そして高校入学。
僕はこのときを待ちに待っていた。新しく出会うクラスメイトたちの中で、何事もなかったかのように一からやり直そう。ひょうきんで、人気者の僕に戻ろう。僕の胸は、そんな期待に高鳴った。
ところが、ことはそう上手くは運ばなかった。人と付き合う上で、約一年半というブランクは、自分で思っていた以上に長かった。笑顔の練習、自然な振る舞いの練習を積み重ねる中で、その都度何百回、何万回と繰り返した、うまくできないことに対する自己否定。その結果、知らず知らずのうちに、僕の苦手意識は恐ろしく深いところにまで根付いていたのだ。
結局僕は、高校での心機一転にも失敗した。
周りで次々と新しい友達関係ができあがる中、僕はというと、気付いたときには中学のときと変わらず、一人ぽつんと教室の中に孤立してしまっていた。
友達を作れない原因は間違いなく僕にある、自分の居場所を見つけられない原因は、間違いなく僕にある。それはもう十分に分かっていた。誰かのせいにするつもりなんてなかった。ふがいない自分のことは誰よりよく分かっていた。だけどそのときの僕は、もう一度自分を奮い立たせて立ち向かうには、心底疲れ切っていたのだ。誰と話すでもなく、ただ一人下を向いているためだけに学校へ通うことにも、クラスメートたちから同情なんかされないように、精一杯強がっていることにも、心底、疲れ切っていたのだ。
そんなわけで入学して間もなく、僕は自然と、あれこれ理由をつけては学校を休むようになった。そしてついには、いわゆる「登校拒否児」となってしまったのだった。
一方、父さんと母さんはというと、少しの間、そのことに気がついていなかった。
二人の名誉のために言うと、二人は決して僕に無関心だったわけじゃない。むしろ、僕の落ち込みように随分と神経をすり減らして、心配してくれていた。僕と同じように、高校入学というチャンスに賭けていた。新しい環境でもう一度、活き活きとした僕に戻ることを、切実に願ってくれていた。僕自身、そのことは誰よりも分かっていたのだ。だからこそ、高校でもうまくやれてないなんて、二人に打ち明けることはできなかった。
そこで、僕がとったとんでもない行動はと言うと……朝、制服に着替えて、カバンを手に、「行ってきます」と、家を出る。で、さも学校へ行ったかのように見せかけて、そのまま裏庭の物置の中に潜伏するのだ。ただでさえ小さな物置、中にはぎゅうぎゅうに物が詰め込まれていたから、隙間に入り込むのは至難の業だった。ましてやそこでしばらくの間じっとしてる、なんていうと、不自然な体勢を強いられた身体のあちこちが、段々と悲鳴を上げ始め、忍耐力とのギリギリの攻防戦になる。
でも、そんな状態で三十分も我慢すれば、妹や弟は学校へ、両親はそれぞれ仕事に出かけるから、家の中は無人になる。僕はそのタイミングを見計らって、家の中に戻るのだった。
初めのうち、うまく行っていたこの方法。けれども、当然のことながら一週間もすると学校の先生から、
「家入君、最近学校に来てませんが」
なんて連絡が入ることとなり、僕の秘密はたちまち家族中に、バレてしまったのだった。
「お前は……なんしよんか!」
半ば呆(あき)れ気味に、父さんの激しい檄(げき)が飛んだ。
「……お父さん、そんな怒ったら、一真が何も言えんようになるでしょう」
僕をかばって、父さんをなだめようとする母さん。そんな二人の間にも、何となくぎくしゃくした空気が流れて、色んな後ろめたさから、僕はうつむいたまま、顔を上げられなかった。
体育祭から脱走
風が吹いたら遅刻して、雨が降ったらお休みで──。
高校一年生の一学期が終わった段階で、たぶんハメハメハ大王の子供より僕の出席率は低かった。
家族に散々心配かけて、父さんには毎日のようにせっつかれて、それでも頑なに学校に行くのを拒んでいた。でも、そんな僕とはいえ、心の底では当然、学校に行かなくちゃ、という思いだけは人並みにあって、それができていないという後ろめたさも、絶えず心の中に影を落としていた。だから、決して僕だけじゃない、みんなも「休み」と決められた夏の一ヶ月間、僕の気持ちは、少し楽になった。
でも、そんな夢のような一時もあっという間に過ぎ去って、九月。
二学期が始まると同時に、学校で僕を待ち受けていたのは「体育祭」という、さらなるジゴクだったのだ。
当時の担任の先生や、父さん、母さんは、僕を気にかけてくれるばっかりに、「体育祭には出てこいよ」とか、「一年に一回しかないんやけん」とか、体育祭への参加を強く勧めてくる。
でも、正直なところ僕にとってそれは、とんでもない話だった。何しろ体育祭、なんて言うからには基本は団体戦。通常の学校生活以上に強いチームワークを求められる場なのだ。そんな場所に突如、ぶっつけ本番で参加したとして、クラスメイトの名前もほとんど知らない僕が、到底うまくやれる自信なんてなかった。そうかと言って、それを無言でカバーできるだけの、圧倒的な運動能力も、残念ながらなし。学校生活を取り戻すきっかけとしての体育祭は、僕にとってあまりに高すぎるハードルだったのだ。
でも、一方では、先生や両親が僕のためを思って参加を勧めてくれているということも、十分に分かっていた。それだけに、僕はすっかり途方に暮れてしまっていた。
そんな中、ついに迎えた体育大会当日の朝。
起き抜けに、僕の目に飛び込んできたものは、居間でビデオカメラと三脚を念入りに点検する父さん。台所では、母さんが豪勢な弁当を重箱に詰めていた。結局、それまで一度も「不参加」の明確な意思表示をできなかった僕のせいで、家の中はすっかり、体育祭モードに突入していたのだ。
……愕然とした。何とか仮病を使って休もうと、前の晩から布団の中であれこれ画策(かく さく)していたのに、いざそんな両親を目の当たりにすると、今さらとてもじゃないけど「休む」なんて言えない雰囲気だったのだ。
仕方なく僕は、限りなく重々しい動作で顔を洗って、限りなくスローなペースで朝食をとって、入念過ぎるほど入念に身支度を整えた。そうこうしている間に、気付いたら体育祭終わってた! なんてことにならないかな、と淡い期待を抱いていたものの、ついにはそんな僕を見かねて、父さんが一言。
「一真、ぐずぐずするな。早く行け」
「は、はい……」
やむを得ず僕は、靴を履き、追い出されるように家を出ることになったのだった。
「……行ってきます」
絶望的な気分で言うと、閉めかけた玄関の引き戸の向こうから、母さんの声が聞こえた。
「行ってらっしゃい。お父さんとお母さんは後で行くけんね、頑張ってね」
その数時間後。
本当なら高校で体育祭に参加しているはずだった僕はというと……たった一人、見知らぬ町の、寂れた無人駅に立っていた。
(ここは……どこやろ?)
二人がけのベンチが向かい合わせに二脚、その脇に灰皿がひとつ置かれただけの、僕の家くらいの大きさしかない、小さな駅舎。壁に画鋲で留められた時刻表は日に焼けて、ところどころが破れていた。
マジックやボールペンで、色んなところに書きなぐられた落書き。はめ込み窓の木枠の上に、丸まって落ちている小さな蜘蛛(く も)の死骸。
大昔に、時間が止まってしまったみたいなこの駅に、意図せず降り立った僕はというと……真新しいジャージの上下に、真っ白な室内用の上履きを着用。周りとは対照的に、惨めなくらい全身ピカピカ、ピカピカマン。
誰が見ているわけじゃないけど、僕はなんだか無性に気恥ずかしくなって、逃げるように早足で、駅の外へと歩き出した。
……あのとき、父さんに言われるままに家を出て、学校へ向かうまではよかった。久しぶりの学校、久しぶりの教室。緊張しながら教室に入ると、名前も知らないクラスメイトが怪訝(け げん)な顔で僕を見て、そのうち何人かは、おはよう、と声を掛けてくれた。
だけど、やっぱり駄目だった。教えてもらった自分の席について、じっと朝礼が始まるのを待っていると、自分の中で、どんどん不安が大きくなっていくのだ。本当にこのまま、ぶっつけ本番で体育祭に参加するのか? クラスメイトにも、家族にも、僕の惨めな姿を晒すのか?
……それで僕は、逃げ出したのだ。
先生が教室に来る前にトイレへ立つと、しばらくの間、大の部屋に息を潜めて潜伏した。始業時間を知らせるチャイムが鳴って、それまでがやがや騒がしかった外が、急にしんと静かになったその瞬間……今しかない、そう思った。で、脱走。
校門には先生が立ってることが分かっていたから、僕は上靴のまま、トイレの窓から、校舎の外へ抜け出したのだ。ところが、そんな僕の目の前に新たに立ちふさがっていたのは、高さ約二メートルほどの、緑色のフェンス。少し先へまわれば、裏門から出られる。でも、誰かに見つかれば、捕まってしまう……仕方なかった。僕は必死の思いで、そのフェンスによじ登り、外へ出たのだった。
それからしばらく、僕はずっと、誰かに追いかけられているような気がして、ただがむしゃらに走った。息が切れて、胸が苦しくなった。早く、誰にも見つからないところに行きたかった。だからといって、家に帰るわけにもいかない。
そんなわけで、気がついたときには僕は電車に飛び乗っていた。とにかく遠くへ行けば、何とかなると思ったのだ。
一駅、また一駅とやり過ごすうち、僕は少しずつ落ち着きを取り戻していった。もうきっと、誰にも見つからない、そんな思いが無意識に張り詰めていた緊張の糸を緩めていった。
あのとき迷う暇はなかった。あの窓から逃げ出す以外に、僕に選択肢はなかったのだ。大変なことをしてしまったという後悔なら、もちろん少しは心の中にあった。でもそれだけに、もう後戻りはできない、このまま進み続ける以外に選択肢はない。そんな状況の中で、僕は不思議と、ちょっとだけワクワクしていたのだった。
……ところがそうして一時間、二時間と列車に揺られるうちに、窓から眺める景色はどんどん見たことのないものに変わっていった。町を抜け、住宅街を抜けて、見知らぬ田舎町を通り過ぎて……そこへきて僕は急に、とてつもない心細さに襲われた。
遠くまで行こうと思った。そうすれば何とかなると思った。でも、こうして実際に遠くまで来た僕、これから、どうしよう? たどり着いた見知らぬ街で、家を捨て、家族を捨てて、新しい生活を営む……なんて、まさか。そんなこと、初めからこれっぽっちも頭になかった。
……愚かだった。ただ身一つで遠くまでやってきたところで、どうにもならないということに、そのときになってようやく気が付いたのだった。そこで僕は、ついに電車を降りた。
そんな経緯(いき さつ)でたどり着いたのが、この寂れた無人駅だった。
いっそのこと、このまま反対側のホームから電車に乗って、家へ帰ろうかと考えた。でも……それはできない。僕がすっかり体育祭に参加していると思い込んでいる父さんと母さんは、ビデオカメラと豪勢な弁当を抱えて、僕のいない学校へ行ったに違いなく、そこでちょうど今頃、一真君が行方不明です、と告げられ、愕然としているだろう。そんな二人に合わす顔なんてない。
駅から一本外へ出ると、見渡す限り、だだっ広い田んぼが広がっていた。そんな駅と田んぼを横切るようにして通っている、細い一本道を、僕はとぼとぼと、あてもなく歩いた。
青々とした稲は、風を受けては波立った。その上を、泳ぐように飛び交う、無数のトンボ。
(なんで、逃げちゃったんだろ……)
僕はただ、後悔していた。できることなら時間を巻き戻したかった。体育祭から逃げ出す前の、学校に。……僕にとって最初で最後のチャンスだった、高校の入学式の日に。……中学の友達と喧嘩をした、あの日に。
どれだけ悔やんでも、懺悔しても、二度と帳消しにできない苦い思い出が次々に蘇って、気がつくと僕はボロボロに泣いていた。情けない自分、惨めな自分が憎かった。分かっているのに、どうにもできない自分が憎かった。裏切ってしまった父さん、母さんのことを思うと、余計に涙がこぼれた。
九月の終わりだというのに、その日はとても暑い日で、頭の上からは秋の太陽がじりじりと照りつけた。そんな中を、ただ何時間も、とぼとぼと泣きながら歩いた。すると、途中ふと喉の奥に鉄臭さを感じた。恐る恐る顔に触れると、手の平が真っ赤に染まって、ギョッとした。いつの間にか僕は、大量の鼻血をダラダラ垂れ流しながら歩いていたのだ。カバン一つ持っていなかった僕は、仕方なくジャージの袖で流れ出る血を拭ったけれど、なかなかすぐに血は止まらず、ついには白い上履きにまで、ポトポトと滴り落ちた。大量の涙と鼻血で、僕の顔はたちまちぐしゃぐしゃになって、そのあまりの情けなさに、僕はさらに泣いた。泣いて、泣いて、泣いて……家へ帰ろうと思った。
そんなこんなで何とか家まで帰りついた頃には、あたりはすっかり夜になっていた。そっと玄関を開けて家の中に入ると、薄暗い居間で、母さんが泣いていた。テーブルの上には、風呂敷で包まれたままの重箱が、そのままぽつんと置かれていた。
ついに退学へ
僕は当然、父さんに物凄く叱られると覚悟していた。でも、意外にも父さんは、帰ってきた僕に、何も言わなかったのだ。
僕はそのことがずっと不思議だった。子供の体育祭を見に、ワクワクしながら学校へ向かったのに、いざやってきてみると、お宅の息子さんいません、なんて衝撃の事実を告げられる。日ごろ、あれだけ怒りっぽかった父さんが、あのときだけ、どうして怒らなかったんだろうと、不思議でしょうがなかった。
その謎が、最近になってようやく解けたのだった。
「一真が帰ってきても、絶対に怒鳴らんで。怒鳴ったら離婚します」
と、僕が家に帰る前、母さんが父さんに話をつけていてくれたらしいのだ。
そんなわけで、父さんも母さんも、体育祭から僕が逃げ出したことについて、びっくりするくらい寛大だった。
「……どこ行っとったん。おなかすいとらんの?」
僕が帰るなり、何も聞かずに夕飯の支度をしてくれた母さん。テレビを見ながら、いつもと同じように、コーヒーを飲む父さん。でも、母さんの泣きはらした目や、どこか落ち着かない父さんの雰囲気に、本当は僕に言いたいことがたくさんあるんだ、ということはすぐに分かった。それを、言わないでくれていることも、すぐに分かった。
(散々心配かけたのに……)
そのことで余計に、僕の罪の意識は大きくなった。
そこで、僕はついに一念発起。両親への罪滅ぼしという気持ちもあって、再び、毎日ちゃんと学校へ通うようになったのだ。……と言っても、クラスメートと上手くしゃべれないのには変わりなかったから、相変わらず友達はできないまま。やむを得ず僕は、ただ黙々と勉強した。
休み時間も、弁当の時間も、ひたすら教科書と向き合い、シャーペンを動かす。しばらく学校を休んでいた間に、どの教科もさっぱり授業についていけなくなってたから、遅れを取り戻すためにも、僕はとにかく勉強に明け暮れた。
そんな僕に、ミラクルが起きた。
なんと、その数週間後に行われた定期テストで、いきなりの総合点、クラス三位。これには僕もびっくり、クラスメイトもみんなびっくりだった。
「家入君って勉強できるんやねえ」
なんて、名前も知らないクラスメイトが話しかけくれたりもして、なんだかちょっと嬉しかった。
ところがその日の放課後。
「家入、ちょっと来い」
ホームルームの後、担任の先生に呼ばれて職員室へと向かうと、先生は僕の顔を見て、おもむろにこう、切り出したのだった。
「……テストについて、何か言いたいことはないか」
「……え、どういうことですか?」
質問の意味を、僕はすぐには理解できなかった。
「……この前のテストは、本当にお前の力でやったんか?」
「え……」
長い間学校を休んでいた生徒が、定期テストでいきなり良い点を取るなんて、先生にとって完全に予想外なことだったのだろう。そのうえ相手は体育祭を上靴で逃亡するような、何をしでかすか分からない生徒。僕はあからさまにカンニングを疑われていたのだ。
その日、帰宅した僕が母さんにそのことを打ち明けると、母さんは僕以上に腹を立てて、すぐに先生に抗議の電話をかけてくれた。母さんの剣幕に負けてか、先生は繰り返し謝ってくれて、先生と僕は間もなく和解。
だけど、結局は僕自身の弱さが原因で、しばらくすると、僕は再び、学校を休むようになってしまったのだった。
そんなこんなで結局半分近く休んで過ごした二学期を終え、冬休みを終えて、三学期。そこにきて僕は、ついにどうにもできない深刻な壁にぶつかってしまったのだ。当然といえば当然なんだけど、出席日数が足りずに、二年生に進級できないと告げられたのだ。簡単に言うと、留年。
でも実際問題、僕の家には人より余分に高校へ通うような、経済的な余裕はなかったし、僕自身、同じ高校の中でもう一回一年生をやり直すだけの、精神的なタフさに欠けていた。そんなわけで、一年が終わるのを待たずして、ついに僕は高校を途中退学することになったのだった。
押入れにこもってパソコン三昧
高校生だった一年間、とにかく僕は学校が嫌で嫌で仕方なかった。毎日が日曜ならどんなにいいだろうと思っていた。
でも、いざ学校を辞めてしまうと、学校を辞めたからって、そう簡単に自由が手に入るわけじゃないんだってことに、今さらながら、気付かされたのだった。
普通、高校生なら学校にいるはずの時間に外を出歩いたりなんかすれば、近所の人に目撃されて、「家入さんちの一真君、高校やめたちいう話よ」なんて後ろ指差されるに決まっている。そうかと言って、一般の高校生に合わせて夕方に外出すれば、かつての同級生とばったり出会って、気まずい思いをするかもしれない。そんなことを考え出すと、いつになっても外に出るタイミングをつかめず、結局はほとんど毎日を、家に閉じこもって過ごすようになってしまったのだった。
そんなこんなで、めっきり病的にインドア派になってしまった僕にとって、当時、ただ一つの心のより所といえば、高校に入学して間もなくの頃、父さんがなけなしの金をはたいて買ってくれた、一台の中古パソコンだった。
PC-9801 FX。
その頃は主に業務用に使われていたデスクトップ型パソコンだ。ハードディスクは40MB、内蔵メモリはなんとたったの1MBという、今ではとても考えられない、ひどいものだったけど、当時はそんなパソコン、しかも中古でも、一台、三~四十万はしたのだ。パソコンは恐らく僕の家で、父さんの仕事に使うトラックに次いで、高価な買い物だったに違いない。
その当時、ウィンドウズなんてまだ当然、発売前だったから、パソコンを買って真っ先にやるのはMS-DOSというOSをフロッピーディスクからインストールする作業だった。パソコンにフロッピーを差し込んで、マニュアルに沿ってキーを叩く……初めて我が家にパソコンがやってきた日、僕はただこれだけのことをやるのにも、無性にワクワクした。
最初はなんでもないただの四角い箱、それが薄っぺらなフロッピーから情報を読み込むことで、色んな動作を可能にしていく。文書作成、スクリーンセーバー、ゲーム……モニターの中で動く色んなアプリケーションを、遊び感覚で操作しているうちに、僕は自然と「プログラム」に興味を持つようになっていった。パソコンを起動する、パソコンを終了する、そんな基本的な動作の一つ一つを指示する、プログラム。
何しろ時間なら余るほどあったから、僕は早速勉強を開始した。高校受験のとき、父さんが押入れを改造して作ってくれた僕の部屋(ベッドと勉強机が一体となった、ロフト状の異常に狭い部屋だった)に、朝も、昼も、夜も、ひたすらこもり切って『はじめてのC』という有名なプログラミングの入門書を、穴が空くほど読みふけった。プログラムとか、C言語とかいうと、いかにも難しそうに聞こえるけど、分からないことがあれば分かるようになるまでひたすら本を読み込んで、うまくいかなければうまくいくまでやりなおす。そうこう繰り返しているうちに、いつか必ず動くようになる。
ましてや学校とか、友達とか、複雑で答えのないものに、ずっと悩まされてきた僕にとって、マニュアルがあって、法則があって、しかも完成形があるプログラミングという作業は、心の底から楽しかった。
同じ頃、父さんの勧めもあって、パソコン通信も始めた。
「一真、パソコン通信、やってみらんか」
最初、父さんにそういわれたとき、僕は実を言うとそんなに乗り気じゃなかった。何しろパソコン越しとは言っても通信は通信、人付き合いは人付き合いなわけで、僕の一番の苦手分野。積極的にやろうとは思えなかったのだ。ところが、そんな僕を一層気にかけて、父さんは強引にパソコン通信の設定をしてくれた。「……ピーヒョロヒョロ、ヒュルヒュル~」、妙な音を立てて接続状態になると、モニターには、初めて目にする電子掲示板の書き込みが、一覧となって表示された。
〈○○さんこんにちは〉
〈皆さんはじめまして〉
〈△△さん、お久しぶりです!〉
……ものすごい衝撃だった。いつもと変わらない僕のパソコン、僕のモニターの中で、たくさんの人たちが挨拶を交わし、親睦を深め、時に強い口調で盛んに議論を交わしているのだ。顔の見えない人たちの膨大な量のやり取りに僕はただ圧倒され、同時に、ここでなら……と思った。引きつった顔でしか笑えなくても、ここでなら言葉をやり取りできる。口の軽い僕でも、文章でならやり直せる、そう思った。
そこで僕は、一通り、書き込みに目を通した後で、恐る恐る「はじめまして」の挨拶を書き込んでみた。
〈はじめまして、カズマです、よろしくおねがいします〉
当たり障りのない無難な挨拶だった。するとその数時間後、再び掲示板に接続した僕の目に飛び込んできたものは、
〈はじめまして、カズマさん〉
〈こんにちは、カズマくん〉
そんな、僕への返事の書き込み。
見ず知らずの人たちが、僕を無条件に受け入れてくれている。返事を返してくれている。
……嬉しかった。
活字であったとしても、久々に家族以外の誰かと言葉を交わした、そのことは少しだけ僕の自信になった。
そんなわけで、僕はたちまちパソコン通信に夢中になっていったのだ。
自作のスクリーンセーバーが雑誌に!
「こんなスクリーンセーバー作ってみました。ご自由に使ってみてください」
プログラムを組んで、掲示板で公表する。するとその数時間後には、いいですね、とか、ここが間違ってますよ、なんて、誰からか、何かしらの返事が届いている。
パソコン通信を始めて以来、僕には、同じようにプログラムを学ぶ、仲間ができた。作ったプログラムを評価し合ったり、分からないところを教え合ったり。そんな、仲間同士のコミュニケーションを通して、自分で言うのも何だけど、僕の技術はめきめきと向上した。
そんなある日、僕の元に一通のメールが届いた。差出人はVector編集部。内容は、確かこんな風だった。
〈腐乱栗★ン(というのは僕の過去の恥ずかしいハンドルネーム)様。あなた様の『恐怖面スクリーンセーバー』を今回創刊致しますソフトウェア集、Vectorにて、掲載させていただきたくご連絡させていただきました……〉
無料・有料ソフトウェアのダウンロードサイトとして、今も多くの人に利用されているVector。そんなVectorも、かつては年に二度、ソフトウェア集として書店で販売される書籍だった。その、記念すべき創刊号に、僕の作ったスクリーンセーバー、その名も「恐怖面スクリーンセーバー」が収録されたのだ。
当初、打診のメールを受けた僕は、一気に舞い上がった……舞い上がった一方で、実際にその本が発売されて、ちゃんと収録されていることを確認するまで、正直、半信半疑だった。何しろ、その恐怖面スクリーンセーバーは、ドット絵で描いたリアルな人の顔が、血を吐きながら次々と画面中に出現、しかも一つ一つ、どアップになって迫ってくるというひどいもので、作者の僕自身、本当にそんなもの収録されるのかと、ずっと疑問だったのだ。
ところがウソでも何でもなく、恐怖面スクリーンセーバー(作者・腐乱栗★ン)は、確かに発売されたVector創刊号に、収録されていたのだった。
(やったー!)
本当に、嬉しかった。こんなものを収録してくれたVectorさん、ありがとう! たとえ誰も使ってくれなくても僕は十分満足です。誰かがちょっとでも見てくれたら、気持ちわるっ、なんて眉間にしわ寄せてくれたら、僕はもうそれだけで十分です……なんて思っていたんだけど、蓋を開けてみたら意外にも、恐怖面スクリーンセーバーは好評だったのだ。
当時僕は、恐怖面スクリーンセーバーのデータの仕様を公開し、他の人が自由に絵柄を差し替えることが出来るようにしていた。すると、電子掲示板では、恐怖面画像を、可愛い猫に置き換えたものや、キャラクターのイラストに置き換えたものなど、「恐怖面スクリーンセーバー用オリジナルデータ」とされる、他の人が作った、新しいデータが、次々と公開されだしたのだ。
僕の作ったものが、見ず知らずの人の手へ渡り、ちょっとだけ形を変えて、もう一度僕の前に現れる。
……僕は震撼(しん かん)した。そこに言葉はないけれど、それは紛れもないコミュニケーションだと、僕は感じたのだ。同じようにプログラムが好きで、新しいものを作り出すことが好きな、作り手と作り手、プログラマーとプログラマーの間で交わされる、最もシンプルで、そして非常にカッコイイ、コミュニケーション。
学校も辞めてしまって、ろくに家の外にも出なくなった僕は、世の中と一切、接点を持たなくなってしまっていた。そのことで、色んなものに縛られなくて良くなった反面、何をしても、何を言っても、誰からも評価されない、認められなくなってしまった。かろうじてでも学校に在籍していた頃には気づきもしなかったけど、誰かに認められる、評価されるってことは、人間が、人間らしく生きていく上で、かなり重要な要素だったんだと僕は実感していた。だからこそ、自作のプログラムが思いがけず評価され、出版物に収録された、そのことが、本当に嬉しかった。
山田かまちとの出会い
プログラミングとパソコン通信に明け暮れる毎日、気がつけばそんな状態で約半年が経とうとしていた。
そんなある日。突如、僕の家に思わぬ訪問者が現れた。
「警察署の者です」
僕は相変わらず押入れを改造した自室にひっそりとこもりきり、そんな一大事にも気がつかないほど孤独な作業に没頭していたのだけれど、応対した母さんに後々話を聞くと、警察は、僕の所在をそれとなく確かめてきたのだと言う。どうやら近所の誰かが、
「あの家の長男を最近見ないけど、もしかして殺されているのでは?」
というような、とんでもない通報の電話をしたらしいのだ。
「息子はちゃんと家にいます!」
母さんが断固としてそう告げると、警察はすぐに帰っていったのだそうだ。
パソコンの中における活躍(と言うほどの活躍でもなかったけど)とは裏腹に、近所から「死んでいるのでは」という声が上がるほど、その当時、僕は滅多に外に出ることも、家族以外の誰かと話をすることもなくなっていた。
そんな僕に、ある日突然、母さんが言った。
「一真、天神(てん じん)に出かけるよ。一緒においで」
日が高いうちに外出するのはただでさえ気が引けたし、その上さらに十七歳にもなって、母さんと二人で天神まで出かけるのは何だか無性に気恥ずかしかった。だから、僕は当初かなり渋った。
「僕、行かん」
押入れの自室から少々声を張り上げて、顔も見せずに返事をする僕。大体いつもなら母さんはそれで納得してくれるはず……だったのだけど、その日の母さんはというと、いつになくしぶとかった。
「行、く、よ。一真、ほら、用意せんね」
そんなやり取りを数回繰り返した挙句、結局先に折れたのは僕で、帰りに天神の大きな本屋に寄ってもらうことを条件に、仕方なく僕は、母さんと一緒に出掛けることとなったのだった。
目的は行きの車の中で初めて告げられた。
画家として、詩人として、偉大な作品を多く残しながらも、十七歳……折しも当時の僕と同い年という若さで、エレキ・ギターに感電してこの世を去った天才、山田かまち。天神のとあるデパートで、そんな彼の個展が開催されているというのだ。
山田かまちという少年の名を、そのとき初めて耳にした僕は、そのショッキングな死に関するエピソードに多少なりとも心を動かされたものの、正直なところその他に対しては、ほとんどこれといって興味をそそられなかった。
絵が上手い? 詩が上手い?
「……ふうん」
それが、母さんの話を聞いた僕の感想だった。
ところが、元は嫌々出向いたその個展で、僕は思いがけず、魂を揺さぶられるような強く激しい衝撃を味わうこととなったのだった。
「へぇ、上手いねえ」
僕の横に立って、かまちの絵を眺めながら感想を漏らす母さん。そんな母さんに返事を返すこともできないほど、僕は深く魅せられていた。
力強い生命力、躍動感をそのままに、画用紙に収まりきれないほど大胆に描かれた動物たちの水彩画。今にも動き出さんとする人間の、その周辺の空気をも描き取ったかのような油絵。そして、感じたままに書きなぐられた、あたかも僕に向かって語りかけているような詩と文章。
一枚、一枚と見進めていくうち、知らず知らずのうちに全身には鳥肌が立って、鼓動が早くなっていた。ただ単純に絵が上手いというだけじゃない、美しい言葉を並べているだけじゃない。それ以上に、人の目を惹きつけて止まない得体の知れない力が、かまちの作品にはあった。
彼の絵の中ではいつだって、人や動物が堂々と、あるがままの姿で、何に縛られることなく存在していた。あるがままに横たわり、あるがままに歌い、あるがままに愛し合う。中には頭を垂れ、悲しみに打ちひしがれている者もいるけれど、それさえ、結局は人間の本来の姿なのだと感じさせられた。あるがままに笑う、それと同じように、悩み、悲しむこともまた、人間のあるがままの姿。
言ってみれば、当たり前のことを、ただストレートに表現しているのに過ぎない。それなのに、かまちの作品全てが共通して持つ世界観は、僕たちが生きている日常とはまるで別のもののように感じられた。そして、僕はそこに、激しい衝撃を受けた。
穏やかな海、鳥が飛び、太陽が昇る、人と人とが愛し合う。
極めてシンプル。それなのに、決して手の届かない世界。多くの人はもう随分前に望むことを諦め、そのうちいつしか、理想ですら描けなくなっていた、遥か遠くの世界。
(……僕だってそうだった)
学校の中での取るに足らない出来事で、他人と面と向かって話すことができなくなった。でも本当に深刻な問題は、他ならぬ自分自身と向き合うことができなくなっていたことだった。あるがままに悲しみ、あるがままに苦しむことから逃げていた。情熱も感情も、全て押し殺して押入れにこもり、パソコンに没頭することで一時的に気を紛らわせていた。臆病になる余り、心の中で幸福を望み、誰かと愛し合うことを望む、そんな当たり前のことからも逃げていた。いつしかそんな願いが存在していたことすら、忘れてしまっていたのだ。
けれども、山田かまちという人は、生涯を通して、ひたすら迷いなくそれを求め続けていた。
愛し合いたい。
生きたい。
幸せになりたい。
自由になりたい。
そんな彼の言葉に触れ、世界に触れたことで、僕と同様、それまでずっと薄暗い押入れの中に追いやられていた僕自身の本質的な情熱……あるがままの自分を望み、幸福を望む強い感情が、嫌が応にも湧き上がるのを感じた。言い様のない「焦り」に似た感情が、強く背中を押していた。
「……このままじゃいけない」
どうすればいいのかは分からなかった。けれど、そのときの僕は、ただ無性にそう思った。
このままじゃいけない!
山田かまちの個展に足を運んだあの日以来、僕の生活は一変した。
……と言っても、人と会うのが怖くて外に出られない状況はそうすぐには変えられなかったから、相変わらず外には出ない。そんなわけで、はたから見れば特に変わっていないように見えたかもしれない。でもあの日、天神でかまちの絵に触れたことで、そんな自分ともっとしっかり向き合わなくちゃいけない、と強く思うようになったのだ。
僕という人間は何が好きで、何が嫌いなのか。考えてみると自分でもよく分かっていなかった。何が良くて、何を悪いと思うのか。どんな過去を経て、これからどこへ行こうと思うのか……。
僕は一体何者なのか、ということについて、僕はもっともっと知らなくちゃいけないと思ったのだ。
その結果、僕はあれほど夢中になっていたパソコン通信からもめっきり遠ざかり、その代わりにひたすら絵を描いて、詩を書くようになった。かなり単純で、極端な流され方だけど、でも当時の僕は大真面目だった。パソコン通信で誰かと会話をする、それは間違いなく楽しかった。でも、そんな一時的な楽しみに逃げてる時間なんてない、僕にはもっと、やらなくちゃいけないことがあると思った。
絵、文章。何もないところから何かを創り出す。そうすることで、自分でも見えなかった、自分自身の輪郭(りん かく)が浮き上がってくるような気がした。
僕が、そんなことをただ黙々と続けていたある日。僕と、そして僕の家族にとって、とてつもなく大きなニュースが舞い込んだ。
「おい一真、裕子、真啓。ちょっと話があるけん、こっちに来て座らんか。母さんも、座ってくれ」
父さんに呼ばれて、僕たちは一瞬にして重苦しい空気に包まれた。僕たち、何か悪いことしたっけ……? 無意識に妹に目をやると、妹も僕を見ていて、目が合った。言われたとおり、居間のちゃぶ台の周りに集合。叱られる……全員が、神妙な面持ちで父さんの言葉を待っていた。ところが、そんな父さんの発した一言に、僕たちは驚愕した。
「……引っ越そうと思う」
「えっ? どこに?」
「駅前に高層マンションが建ちよるやろ、母さんと相談して、あそこに家を買うことにしたんよ」
「えええーっ!」
そんなわけで、僕たちは夢のマイホームに、晴れて引越しをしたのだった。
五人家族に2LDKの住まい。決して広いとは言えないけど、元々住んでいた家に比べると、そこは疑いようのない天国だった。カウンターキッチン、フローリング、白く明るい壁紙。僕たち家族が長年夢見ていたもの、でも、自分たちには一生縁がないと諦めかけていたものが、そこにはあった。さらに幸運なことに、長男の特権で押入れじゃない、快適な僕だけの部屋も与えられて、良いのか悪いのか、結果的に僕はますます孤独な作業にのめり込むようになったのだった。
毎日、何十枚と絵を描いていた僕のもとに、あるときふと父さんがやってきて、言った。
「一真、これ、お前にやるから」
手渡された紙袋の中をのぞくと、そこには真新しい油絵の具と、筆と、そしてキャンバスが二枚ほど入れられていた。
「……これ、どうしたん?」
「お前に買ってきた。今日からこれで絵を描かんか」
「えっ……! ありがとう、父さん」
飛び上がるほど嬉しかった。ずっと、いつか油絵を描いてみたいと思っていたのだ。
でも、それを受け取った瞬間、僕は急に、物凄い罪悪感に襲われた。
(こんな高価なもの……)
マンションを買ったばかり、しかも妹も弟もまだ学生で、家計は恐ろしく苦しいはずだった。ただでさえ忙しかった父さんは、引っ越してからというもの、本職のトラック運転手の他に、早朝と深夜、バイトを二つも掛け持ちして、ギリギリまで睡眠時間を削って働いてくれていた。
そんな中で、学校にも行ってない僕は、働こうと思えばいくらでも働けるはずなのだ。一般的には、もう十分にそうしていい年齢だった。でも実際は、朝も昼も夜も、ただひたすら自分のやりたいこと、絵を描いたり、詩を書いたりに励むだけで、父さんと母さんに、負担をかけてばかりいる。
(……僕なんか、これ以上この家にいちゃいけないんだ)
そのとき、僕はとっさに家出を決意した。父さんと母さんを少しでも楽にしたかった。僕なんかに使ってくれているお金は、これから育っていく妹、弟のために使ってくれればいい、これ以上僕ばかり、甘えていてはいけないんだと思った。
翌日、家族が出払っている間に荷造りをした。
二、三日分の着替え。道に迷わないように、地図。雨が降っても風邪をひかないように、折りたたみ傘。地面の上で休憩するときにお尻がぬれないように、レジャーシート。自分で白米を詰めた弁当箱に、麦茶を入れた水筒。……そんなものを、長年使っていた愛用のリュックに一式詰めた。財布の中を確認すると、所持金は二千円ほどしかなかったけど……やむを得ないと思った。何とかなるっちゃ。
全ての荷物を詰め終わったリュックの横に、父さんからもらった油絵の具セットの木箱を添えて、準備は完了した。
(……どこに行くかな)
でき上がった荷物を見ながら、考えた。行く当てはない。ただ、絵を描きながら、日本中を旅しよう、それが、大まかな僕のプランだった。もし、お金に困ることがあったとしても、絵があればたぶん何とかなる。これからは、自分だけの力で、何とか生きていこう。
一通り荷造りを終えると、最後にいよいよ、家族への置手紙の作成に取り掛かった。
〈父さん、母さん、裕子、真啓へ。
今まで有難うございました。
しばらく帰りません。探さないでください……〉
ところがここで、困ったことが起きた。最後なんだから、ちゃんと家族に感謝の気持ちを伝えよう、頭ではそう思うのに、いざ手紙を書こうとすると、子供の頃の楽しかった思い出や、何気ない家族の笑顔が一つ、また一つと思い出されて、胸がいっぱいになってしまうのだ。
こんなにも愛されて育った僕……そんな僕を失った後の家族は、どれほど悲しむだろう。小さい頃は、ずっと一緒に遊んでいた妹。僕のことを慕って、僕の真似ばかりしていた弟。僕たちのために、懸命に働いてくれた父さん。それから、優しかった母さん……そんなことを思うとつい、
(うっ、ぐぐっ……)
僕の目からは滝のように涙が溢れ、手元の置手紙はたちまち、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになってしまうのだった。
結局、何度挑戦しても、置手紙を最後まで書き上げることはできなかった。そんなわけで、僕の家出計画はあえなく頓挫。しょうがないので、ついさっき自分で詰めた白飯を食べて、水筒の麦茶を飲み、おなか一杯になったところでWANDSの『時の扉』を、鼻をすすりながら口ずさんだ。
十七歳の、秋のことだった。
次の章:第三章 長いトンネル
目次
全文公開にあたって
プロローグ
第一章 貧乏な家に生まれて
第二章 「ひきこもり」だったあの頃
第三章 長いトンネル
第四章 起業前夜
第五章 ペパボ黎明期
第六章 成功、そして未来へ
エピローグ
新装版にあたって
解説 佐々木俊尚
もしよろしければサポートお願いします!
